「固定資産税ってよくわからない・・」
「固定資産税が安くなるポイントがあるなら知りたい」
この記事では、このような疑問を持つ人に向けて、平屋の固定資産税について解説しています
家を購入すると、1月1日時点で名義のある方に課税されるのが固定資産税
税額は、土地の評価額と、建物の評価額で決定されるよ
建物の評価額は、勾配天井の角度・外壁や屋根材・太陽光発電の種類によって値段が上がるので注意が必要!
また、新築の場合、軽減措置が適用されますが、一定の面積を超えた分は固定資産税が軽減されません
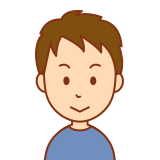
広い平屋を建てたら・・後から後悔した!
なんてことも・・
本記事では、「知らなきゃ損!固定資産税が安くなる11のポイント」をご紹介しています
- 固定資産税はどうやって決まるの?
- 平屋の固定資産税は2階建てに比べて高い?
- 平屋の固定資産税を安くする11のポイント
- 固定資産税は何坪から上がる?
- 35坪の平屋の固定資産税を例に解説
固定資産税についてしっかりと理解を深め、後悔のない家づくりをしましょう
固定資産税とは?
家を購入すると、土地や建物の所有者に毎年かかってくるのが、固定資産税
固定資産税とは、土地や建物にかかる税金のこと。
毎年1月1日に名義のある人に税金がかけられます
固定資産税の税額は
- 土地の評価額
- 建物の評価額
によって決まり、課税の主体は、住宅のある市町村です
毎年、4月~6月頃に、市町村から「納税通知書」が自宅に届きます
固定資産税の計算方法
固定資産税評価額は、各市町村が「固定資産評価基準」を元に、土地や建物の評価額を個別に決められ、次の計算式で算出されます
固定資産税=固定資産税評価額×標準税率1.4%
少しややこしい計算式ですが、簡単に言うと、固定資産税評価額は
- 土地の評価額・・・時価の7割程度
- 家の評価額・・・実勢価格の5~6割程度
購入価格がそのまま評価額にはならない点に注意しましょう
標準税率は1.4%ですが、住んでいる市町村によって1.5%や1.6%のところもあります
土地と建物で、固定資産税評価額の計算方法は異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください
<土地>
土地の評価額=土地の面積×路線価
<建物>
家屋の評価額=評点1点あたりの価額×床面積×単位面積あたりの再建築費評点×経年減点補正率
平屋と二階建てならどっちが安い?
総坪数(延べ床面積)が同じ場合、平屋のほうが2階建てより固定資産税は高くなります。
理由は、同じ延床面積なら
- 平屋のほうがより広い土地が必要
- 壁・屋根材が多くなるから
単純に、2階建てと同じ床面積なら、2倍の土地が必要になります
建物も、屋根や壁の分量が多くなりやすいため、平屋のほうが高くなる傾向にあります
坪数が大きくなるほど、平屋のほうが割高に!
土地も建物も、コンパクトにすることで固定資産税を安くできるよ
平屋の固定資産税を安くする11のポイント
平屋の固定資産税を安くするには、建物と土地の評価額を低くするのがポイント
知らなきゃ損!固定資産税を安くする11のポイントをまとめました
- コンクリートより木造住宅にする
- 土地も建物もコンパクトな造りに
- 外壁材のポイント
- 勾配天井は緩やかに
- 軒の出は短く
- 屋根材のポイント
- 屋根形状にも注意
- カーポートやガレージの注意点
- 高価な住宅設備を導入しない
- 土地の評価額が低いところに建てる
コンクリートより木造住宅にする
建物は、木造のほうが、コンクリートに比べ固定資産税が安くなります
平屋は2階建てに比べ耐震性が高いので、木造でも、安全な家を建てることができます
シンプルでコンパクトな作りにする
土地と建物の評価額は、面積が広くなるほど値段が高くなります
つまり、建物も土地もよりコンパクトにするのが固定資産税を安くするポイント
広い家は憧れますが、いたずらに広げすぎないようにしましょう
勾配天井は緩やかに
同じ屋根材でも、屋根の勾配で固定資産税が変わるので注意が必要
- 急勾配・・・高い
- 緩やかな勾配・・・安い
緩やかな勾配天井にするのがポイントです
外壁材のポイント
外壁材は、家の評価額が高い順に、このようになります
ガルバリウムにすると、固定資産税が安くなります
- タイル
- 漆喰
- サイディング
- ALCパネル
- ガルバリウム
軒の出は短く
軒の出が長ければ長いほど固定資産税が上がります
- 軒の出が長い・・・高い
- 軒の出が短い・・・安い
屋根材のポイント
外壁と同じく、屋根材もガルバリウムが一番安くなります
固定資産税が高くなる、屋根材の順番はこちら
- ソーラーパネル一体型
- 瓦
- ストレート
- ガルバリウム
屋根形状にも注意
屋根の形状は、片流れ屋根にすると、固定資産税が安くなります
高い順に並べたので、参考にしてください
- 腰折れ
- 越屋根
- 切妻
- 寄棟
- 片流れ
カーポートやガレージの注意点
カーポートやガレージにも注意しましょう
- 1枚の屋根を柱で支えるタイプのカーポート・・・固定資産税がかからない
- 3方向を壁で囲まれているガレージタイプ・・・固定資産税の対象に
壁に囲まれているタイプのビルトインガレージも対象になるので、注意が必要です
高額な住宅設備を導入しない
高額な住宅設備を導入することで、家の評価額が高くなる傾向にあります
特に、次の4つのハウスメーカーは、固定資産税が高くなることで有名です
- ヘーベルハウス:ヘーベル板
- 一条工務店:屋根一体型太陽光発電・外壁タイル
- 三井ハウス:全館空調
- 住友林業:ビッグフレーム構造
ただし、このようなメリットも・・!
例えば、一条工務店の場合メリットもあります
- 屋根一体型太陽光発電・・・電気代が安くなる
- 外壁タイル・・・外壁の塗り替えが一生不要
それぞれのメリット・デメリットや、将来的なランニングコストなども考えた上で決めましょう
土地の評価額が低いところに建てる
そもそも土地の評価額が低いところに平屋を建てれば、評価額を抑えられます
土地の評価額=地価
なので、駅近の土地より、少し郊外の土地を選ぶほうが、土地の評価額が安くなります
固定資産税は何坪から上がる?
新築住宅には、固定資産税の軽減措置があります
ただし、一定の坪数を超えた分は軽減税率が適用されないので、注意しましょう
新築なら固定資産税が軽減される
新築住宅の場合、3~5年間、固定資産税は軽減税率が適用されます
軽減期間は、住宅の種類で異なります
| 住宅の種類 | 軽減期間 |
| 一般的な戸建て | 新築後3年間 |
| 長期優良住宅 | 新築後5年間 |
| 耐火・準耐火構造の 3階建て以上のマンション・戸建て | 新築後5年間 |
| 長期優良住宅の 3階建て以上のマンション・戸建て | 新築後7年間 |
土地が60坪、建物は36坪以上で固定資産税が上がる
正確には、土地は60.5坪を超える部分、建物は36坪を超える部分には軽減税率が適用されません
坪数別の固定資産税のざっくりとした計算式は、こちらを参考にしてください
<土地>
| 土地 | 本来の税率 | 軽減措置 |
| 200㎡(約60坪)までの小規模住宅用地 | 評価額×1.4% | 6分の1 |
| 200㎡(約60坪)を超える一般住宅用地 | 評価額×1.4% | 3分の1 |
<建物>
| 建物 | 本来の税率 | 軽減措置 |
| 居住面積120㎡(約36坪)までの部分 | 評価額×1.4% | 3年間もしくは5年間は2分の1 |
新築を建てるなら、土地は60坪(200㎡)以下、建物は36坪(120㎡)以下にするのが固定資産税を安くするポイント
35坪の固定資産税をシミュレーション
35坪の平屋の固定資産税は、およそ10万円前後
地域によってかなり違いがありますが、以下の条件でざっくり計算してみたので、参考にしてください
<条件>
- 新築
- 税率1.4%
- 土地の評価額:500万円
- 建物の評価額:2000万円
- 土地にかかる固定資産税…500万円×1.4%÷6=11,000円
- 建物にかかる固定資産税…2000万円×1.4%÷2=140000円
となり、大体、15万円くらいがかかるのがわかります
まとめ
今回は、平屋の固定資産税にフォーカスして説明しました
2階建てよりも固定資産税が割高になる傾向があるものの、ポイントを押さえれば固定資産税を安くできるので、購入前にしっかりと検討しましょう!
平屋を安く建築するにはこちらの記事も合わせてご覧下さい
【PR】タウンライフ


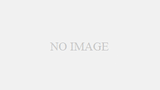
コメント